
敏感な息子に、どう接してあげたらいいんだろう?



HSCの子どもの将来を心配して、干渉しすぎちゃう…
子育てをしている中で、繊細で敏感な子どもの対応に疲れてしまっていませんか?
HSPさんの中には、子どももHSC(Highly Sensitive Child)という方も多いのではないでしょうか。
筆者の場合、自分自身がHSPだと気づいたあとに、赤ちゃんの頃の息子の特徴がHSCにあてはまることを知り、妙に納得した記憶があります。
HSPである私たちが、同じく敏感なHSCの子どもを育てることは、特別な喜びがある一方で、、まわりのママたちよりも疲れを感じやすいのも当然のことです。
この記事では、HSCの特徴や、HSPの親ができる関わり方について、筆者の経験も交えながらお伝えします。
・HSCとは?どんな特徴があるの?
・HSCの子育てが疲れる理由
・赤ちゃんの頃のHSCのサイン
・HSPである親がHSCにできる関わり方



敏感な親子だからこそできる子育てのヒント、一緒に見つけていきましょう!
HSCとは?敏感な子どもの5つの特徴


HSCとは、Highly Sensitive Child(ハイリー・センシティブ・チャイルド)の略で「とても敏感な子」「ひといちばい敏感な子」と訳されます。
アメリカの心理学者エレイン・アーロン博士によって提唱され、約5人に1人の割合で存在すると言われています。
病気や障害ではなく、生まれつき持っている気質の一つです。
HSC(敏感な子ども)の特徴は、次の5つです。
- 刺激に敏感
- 人の気持ちにとても共感する
- 一度に多くのことを処理できない
- 深く考える傾向がある
- 感情の起伏が大きい
1.刺激に敏感
- 大きな音や強い光、人混みなどが苦手
- 服のタグやチクチクした素材、気温の変化などに敏感
- 赤ちゃんの頃から「寝ない」「すぐに泣く」「抱っこじゃないと安心できない」などの傾向も



息子は、1歳で保育園に入るまで「必ず30分で起きる」赤ちゃんでした
2.人の気持ちにとても共感する
- 他人の表情や声のトーン、空気の変化にすぐ気づく
- 誰かが怒られているのを見ると自分が怒られているように感じる
- 「優しすぎる」「繊細すぎる」と言われやすい



息子は、担任が他の子を怒っていると、辛くて泣きそうになるそうです
3.一度に多くのことを処理できない
- 周りでたくさんのことが起きていると、頭が混乱して疲れてしまう
- 初めての場所や新しい環境に慣れるのに時間がかかる
- 行事や旅行の後にぐったりして体調を崩すことも



私もHSPなので、すごく気持ちがわかるんです
4.深く考える傾向がある
- 物事をよく観察し、じっくり考える力がある
- 急かされるとパニックになりやすい
- 慎重で失敗を避けようとするため、新しいことを始めるのが苦手な場合も



息子は、とにかく質問が多い…
5.感情の起伏が大きい
- 喜びも悲しみも人一倍大きく感じる
- ちょっとしたことですぐに泣いたり、怒ったりすることがある
- 自分の感情をどう扱えばいいのか分からず、パニックになることも



激しい感情の変化に振りまわされて疲れます…
HSCの子育ては、なぜ疲れるの?


HSPの親がHSCの子を育てることは、人一倍疲れを感じやすいもの。HSPならではの特性が子育てに大きく影響するからです。
HSCの子育てが疲れる理由は、以下の5つです。
- 共感できすぎて疲れてしまう
- 過保護・過干渉に陥りやすい
- 自分自身の幼少期の頃と重ねてしまう
- 人に頼ることが苦手
- キャパオーバーになりやすい
1.共感できすぎて疲れてしまう
HSPさんは、人の感情や場の雰囲気を敏感に察知し、深く共感する能力を持っています。
だからこそ、HSCの子どもが泣いていると「つらいんだね」「怖かったんだよね」と、まるで自分のことのように感じてしまいがち。
子どもの感情に共感しすぎるあまり、自分も同じように疲弊してしまうのです。
子どもの感情
- 強い感情や不安
- 喜び
- 悲しみ など…
このような共感疲労は、知らず知らずのうちに親の心身をすり減らしていく原因となるのです。
2.過保護・過干渉に陥りやすい
HSPの親は、子どもをあらゆる刺激や危険から守ろうと、過保護・過干渉になってしまうことがあります。
HSCの子どもの敏感さを誰よりも理解できるからです。
例えば…
- 子どもが困らないように、すぐに手助けをしてしまう
- 子どもが辛い思いをしないように、先回りして問題を解決してしまう
- 子どもが嫌がるようなことを避ける
これは、子どもを守りたいという愛情からくる行動ですが、結果として子どもが自分で経験し、学ぶ機会を奪ってしまう可能性があります。
また、親自身も常に子どもの行動を監視し、介入することにエネルギーを使い果たし、疲弊してしまいます。



私は、まさにコレ。夫に「もう少し子どもに任せてもいいんじゃない?」とよく言われます。
3.自分自身の幼少期の頃と重ねてしまう
HSPの親の中には、子どもの頃に自分自身の「敏感さ」で苦労した経験を持つ人も少なくありません。
HSCの子ども見ていると、過去の自分の経験と重ねてしまい、強い痛みや不安を感じることも…。
例えば…
- 「私も小さい頃、人の目が気になって疲れていたな…」
- 「自分だけ、何でも気づいてしまって辛かったな…」
- 「大勢の友達の中には、入れない子だったな…」
上記のような経験をわが子に重ねてしまい「この先、自分と同じように生きづらさを感じないようにしてあげたい」という気持ちが大きくなりがちです。
その結果、必要以上に介入したり、過度な期待を抱いてしまったりすることで、親自身も精神的に不安定になりやすいのです。
4.人に頼ることが苦手
HSPさんは人に頼ることが苦手な傾向があります。
このような理由から…
- 「迷惑をかけたくない」
- 「わかってもらえないかも」
HSCの子育ては、通常の育児に加えて多くの配慮が必要となるため、親の負担は大きいもの。
しかし、HSPさんは限界が近くても、誰かに助けを求めることができず、すべてを一人で抱え込んでしまいがちです。
その積み重ねが、孤立感を深め、知らず知らずのうちに心身のエネルギーを奪っていきます。
5.キャパオーバーになりやすい
もともとHSPさんは、情報や感情を深く処理するため、元々キャパオーバーになりやすい傾向があります。
そこにHSCの子育てが加わることで、さらに多くのエネルギーを消費し、知らないうちに限界を超えてしまうことがあります。
「疲れているのに休めない」「でもやらなきゃ」と心と体がちぐはぐな状態になり、些細なことでイライラしてしまったり、無気力になったりすることもあるのです。
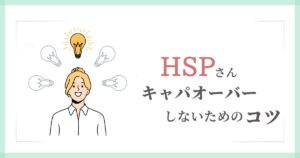
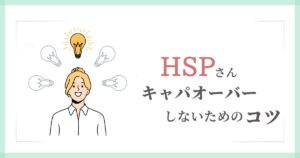
赤ちゃんの頃から感じるHSCのサイン


HSCの特性は生まれつきの気質なので、赤ちゃん期からその兆候が見られることがあります。
「うちの子、少し育てにくいな」と感じていたその感覚は、もしかしたらHSCのサインだったのかもしれません。
1.寝ない・起きやすい・不機嫌が多い
HSCの赤ちゃんは、まわりの刺激にとても敏感なため、寝つきが悪かったり、ちょっとした物音ですぐに目を覚ましてしまったりする傾向があります。
大人にとっては気にならないことにも反応してしまい、なかなか寝つけなかったり、夜中に何度も起きてしまうことも。
例えば、こんなこと
- 音や光
- 温度
- 布団の質感



何度「赤ちゃん 寝ない」で検索したことか…
また、抱っこされていないと不機嫌になったり、特定の体勢を嫌がったりと、泣いている時間が長く、なかなか泣き止まないことも。
これは、些細な不快感にも強く反応してしまうHSC特有の感受性の高さからくるものです。
2.刺激に敏感で、体調を崩しやすい
HSCの赤ちゃんは、緊張しやすく、体調を崩しやすい傾向も見られます。
赤ちゃんが繊細なセンサーで、環境の変化や人混みなど、まわりの空気を感じ取るためです。
例えば…
- 機嫌が悪い日が続く
- よくお腹を壊す
- 熱を出しやすい
頻繁に体調を崩す我が子を見て「どうしてうちの子だけ…」「私の育て方が悪いのかな」と自分を責めてしまうHSPママもいるかもしれません。
HSPである親がHSCの子にできる5つのこと


HSCの子育てに、HSPママが悩みを感じるのは当然のこと。
でも、HSPママだからこそ、敏感な子どもたちの気持ちに優しく寄り添い、サポートできることができるのです。
ここでは、HSPの親だからこそ意識したい5つのことをまとめました。
- 自分の感情と子どもの感情を区別する
- 刺激を減らす環境作りをする
- 子どもに合った対応を見つける
- 親自身のストレスケアを最優先にする
- 理解者を持つ



「全部やらなきゃ」と気負わず、できるところから始めてみてくださいね
1.自分の感情と子どもの感情を区別する
「うちの子が敏感なのは、私の育て方が悪かったから?」と感じてしまうHSPママは少なくないでしょう。
しかし、あなたがどれだけ頑張っても、子どもの敏感さは変わるものではないのです。
なぜなら…
- HSCの敏感さは「親のせい」ではなく、生まれ持った気質だから
- HSCは病気でも、育て方の問題でもないから
- 遺伝的な要素が強く、生まれつきの特性だから
この事実をまず受け入れ「私は悪くない」と自分を許してあげることが、HSCの子育てにおいて最も大切な第一歩です。
2.刺激を減らす環境作りをする
HSCは、音・光・人混み・予定の詰め込みなど、日常の中にあるさまざまな刺激に疲れやすい傾向があります。
そのため、子どもが安心して過ごせるように、刺激を減らす環境づくりを意識することが大切です。
例えば…
- テレビの音量を下げる
- カーテンで光を調整する
- 予定は1日ひとつまでにする
- 人混みを避ける
小さなことでも、子どもの落ち着き方が変わるのを感じられるかもしれません。
3.子どもに合った対応を見つける
HSCと一言で言っても、その敏感さの度合いや、何に敏感かは子どもによって様々です。
育児書通りに試しても、うまくいかないと感じることもあるかもしれません。
だからこそ、子どもを観察し「わが子に合う対応」を見つけていくことが大切です。
こんなことを観察してみよう
- どんな時に落ち着くのか
- どんな刺激を嫌がるのか
- どんな遊びに夢中になるのか。
HSPママは、その“細やかな観察力”が強み。
わが子に合った声かけや接し方、遊び方を見つけていくプロセスを楽しむくらいの気持ちでいると、子育てが少しラクになるかもしれません。
4.親自身のストレスケアを最優先にする
「子どものために頑張らなきゃ」と思うあまり、自分のことを後回しにしていませんか?
でも、親が疲れていると、HSCの子どもはすぐにその空気を感じ取ってしまいます。
だからこそ、まずは自分の休息・癒しが最優先。
例えば…
- 短時間でも一人になれる時間をつくる
- 好きなことをする時間をもつ
- パートナーや家族に頼る
- 睡眠をしっかりとる
親が心身ともに満たされていることで、子どもにも穏やかに接することができ、良い循環が生まれます。



自分を労わる時間を大切に…
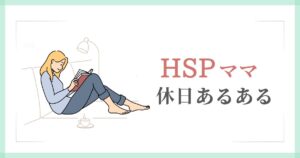
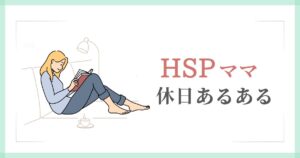
5.理解者を持つ
HSCの子育ては、時に孤立感を感じやすいものです。
周りにHSCへの理解者がいないと「私の育て方がおかしいのか」と不安になってしまうこともあります。
そんな時は、一人で抱え込まず、理解者を持つことが大切です。
例えば…
- HSP・HSCについての本や信頼できる専門家の情報を知る
- SNSやブログで同じ気質のママたちとつながる
- 地域の子育て支援センター
正しい知識を得ることで、子どもの行動をより深く理解し、適切な対応ができるようになります。
そして、困った時に相談できる場所があるという安心感は、親にとって大きな支えとなるでしょう。
まとめ
HSCの子どもの敏感さに寄り添い、常にアンテナを張り、共感しすぎるあまりクタクタに…そんな経験は、HSPママなら誰しもが通る道かもしれません。
しかし、HSPママだからこそ、その繊細な心を深く理解し、温かく育んでいける力があるのです。
HSCの敏感さは、決して「親のせい」ではなく、その子の素晴らしい個性だということを忘れないでくださいね。
そして、敏感な子には、親の深い共感力や優しさが、何よりの支えになります。
完璧を目指す必要はありません。うまくいかない日があっても大丈夫。
まずは「自分を責めない」「休むことも大切」と、自分自身をいたわり、ママが笑顔で過ごせるようにしていきましょう。





